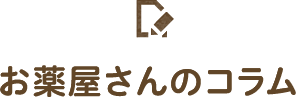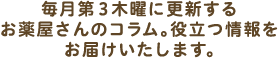お薬屋さんのコラム検索
コタツ寝にはご用心
冬になりコタツが心地よくなりました。ポカポカしてついついウトウト。経験のある方も多いと思います。
でも、これって・・・とても危いことなのです。今回はコタツ寝が招くトラブルについてお話します。
人間は寝ている間に体温を下げ、エネルギーの消費を抑えます。体温が下がるので、汗として皮膚から逃げる水分も少なくなりますが、冬でもコップ1杯程の汗を寝てる間に自然とかきます。
さて、コタツで寝てしまい体温が高い状態が続くとどうなるのでしょうか。
コタツの温度は体温より3~4℃高い約40℃。汗をかくのも当然です。
体温が1℃上がるだけで自然と失う水分量は15%も増えます。体温より3~4℃も高いコタツで長い時間ウトウト・・・汗をかいて水分を失い脱水状態になります。
汗は血液中の水分から作られます。汗をかき続けると、水分が減って粘度が高いドロドロとした血液となります。
つまり、血液が固まる血栓ができやすい状態となるのです。
この血栓が脳や心臓の血管を詰まらせると大きなトラブルにつながります。実際コタツで寝ていて突然死した方もいらっしゃいます。
ホットカーペットを布団の下に敷くのも同じ原理でおすすめできません。
コタツに入る時はお茶などで水分を補給しましょう。
また、ビタミンCを多く含むミカンは、カゼの予防になるだけでなく水分の補給にもなります。冬にコタツでミカンは理に適っているのですね。
2018/01/18
意外に起きる冬の脱水
人間が一日に必要とする水分の量はどのくらいかご存知ですか?
ズバリ答えは2.3リットルです。もちろん飲むだけでなく、ご飯などに含まれる水分も含めての量ですが、大きなペットボトルよりも多い量なのです。
通常は、体内に入ってくる水分と、出て行く水分は同じ量です。しかし、入ってくる量より出て行く量が多くなると、体内の水分が減ります。この出納バランスが崩れた状態が脱水です。
汗を多くかく夏におきるイメージが強いですが、寒い冬でも意外に起こります。
寒いと余計にトイレが近くなるからと飲む水分量が少なくなることや、インフルエンザやカゼによる発熱、ノロウイルスによる下痢などが原因となります。
体内の水分が少ない高齢者や小さなお子さんは特に注意が必要で、脱水状態が続くと、点滴や入院などの対応が必要となることもあります。
脱水を避ける最も有効な方法はやはり水分補給です。
暖かい飲み物は水分を補給してくれるだけでなく、体も暖まる上、胃腸に熱を与えて動きを良くし、消化を助けてくれます。
寒い冬は暖かい飲み物が美味しい季節です。快適に過ごしましょう。
2017/12/21
熱中症にどうして塩分が必要なの?
十分な水分と適度な塩分をとり、熱中症に気をつけましょう!という言葉をテレビなどでよく聞く季節になりました。
水分はわかるけど・・・塩分はどうして?今回は熱中症と塩分についてす。
血圧を上げるイメージがあるため、避けられがちな塩分。
実は、筋肉を動かしたり、体内の水分を維持する役割をもち、人間にとって無くては生きていけないとても重要な成分なのです。
暑い季節になると汗をいっぱいかきます。この汗の中には水分以外に、塩分やミネラル類も含まれています。
汗で水分やミネラルが失われ、不足した状態が熱中症です。
水分が少なくなると、水分を多く含む臓器に大きく影響して症状が現れます。脳だとメマイや立ちくらみ、消化器だとムカムカや吐き気、筋肉だとケイレンですね。
さて、この状態で水分だけを補給するとどうなるでしょうか?
汗で失われたミネラルが水分によって更に薄められるため、熱中症の症状は更に悪化してしまいます。
そのため、水分と供に塩分も摂取してミネラル量を補給する必要があるのです。塩アメや梅干、経口補水液などでミネラルも補給して熱中症を予防しましょう。
血圧への影響が心配・・・という方は、熱中症を防ぐ適切な塩分量はどのくらいかお医者さんに相談してみてはいかがでしょうか。
2017/08/17
ヒートショックはどうすれば防げるの?
前回は気温の変化によりおきる血管の変化についてお話しました。今回はお風呂に入るまでの室温差が血圧に与える影響を考えてみます。
なぜヒートショックは寒い時期に多く起きるのでしょうか?
原因は室温の急激な変化です。
さて、冬場の一般的な室温は、居間 22℃ → 脱衣所と浴室10℃ → 湯船 41℃ → 脱衣所 10℃です。
12℃下がり、31℃上がり、31℃下がります。体周囲の大きな温度変化が血管の収縮や拡張をもたらし、血圧を大きく変動させてヒートショックにつながりやすくなります。
気温が高い夏は、室温差が少ないためヒートショックが起きにくいのです。
10℃以上の温度差は要注意と言われています。この温度差を少なくすることが最大の予防となります。
➀ミニ温風ヒーターなどで脱衣所を温める (室温差を少なくします)
➁ふたを外してお湯をはる (浴室とお湯との温度差を少なくします)
③シャワーを浴室にかける (浴室全体の室温を上げます)
④かけ湯をして体を十分に温める (体とお湯の温度差を少なくします)
⑤40℃未満のぬるめのお湯 (過度な血圧低下を防ぎます)
⑥冷え込む深夜でなく、早めの時間に入浴する (室温差を少なくします)
しっかり対策して快適な冬を過ごしましょう。
2016/12/15
ヒートショックって何?
ここ数年、ヒートショックという言葉を新聞や雑誌で見かけるようになりました。
ヒートショックとは、室温の急激な変化により血圧や脈拍が変動しておきる体の不調のことです。
変動が大きい場合は、脳梗塞や心筋梗塞、意識を失うなどの不慮の事故につながることもあります。
ヒートショックにより亡くなられる方は全国で1万4千人と推定されています。交通事故によって亡くなられる方の実に3倍以上の人数なのです。
起きる時期は11月~2月と圧倒的に冬が多く、寒い時期は要注意です。
体の周囲の温度が下がった時は、血管は収縮して血圧は高くなります。
血圧が急に高くなると心臓や血管に圧力がかかり、脳梗塞や心筋梗塞につながります。
逆に体の周囲の温度が上がった時は、血管は開いて血圧は低くなります。
血圧が急に低くなると、血圧が下がりすぎて血液がスムーズに循環しなくなり、ふらつきや失神につながるのです。
短時間に血管や血圧が大きく変化することがヒートショックにつながるのです。
ではヒートショックを防ぐ対策はどうすればよいの?次回に続きます。
2016/11/17
チャドクガの被害拡大を防ぐには?編
刺されると厄介なチャドクガ。
前回は刺された時の応急処置とその後の対応についてお話しました。
今回は厄介な毒針がついた衣服についてお話します。
チャドクガがまきちらした毒針は、繊維のすきまからも入り込んでしまう極小サイズで目には見えません。
この毒針が衣服についたままだと更に刺されて被害を広げます。
洗濯してもとれないどころか、他の衣服に移ってより被害が広がります。
最も有効なのは、服を捨ててしまうことです。
「モッタイナイ!」「えーお気に入りなのにぃ~」
はい、そんな人がほとんどですよね。
そこで熱による無毒化をおすすめします。
まず手に刺さらないようにゴム手袋をします。
ガムテープやコロコロ、掃除機で吸い取るなどの物理的な方法で取り除きます。
その後、スチームアイロンを当てる、乾燥機にかける、熱いお湯につけるなどで50℃以上の熱を加えます。
チャドクガの毒素は熱に弱いため無毒化できます。毒素を失った針ではカユくなりません。
厄介なチャドクガがいるツバキやサザンカの近くは注意しましょう。
2016/07/21
熱中症予防にエアコンが効果的なのはなぜ?
テレビで熱中症に注意を呼びかける季節になってきました。室内での熱中症予防には、エアコンが効果的です。
でも、エアコンはどうして効果的なのでしょうか?
人間は汗腺から汗をかいて体温を下げます。
この汗、元々は血液中の水分であることはご存知でしょうか?血液中の水分を吸い上げ、汗腺から汗として出しているのです。
室内の温度が高いと、皮膚は気温が高いという情報を脳に送り、脳は汗を出す指令を送ります。
汗をかくためには、皮膚に近い血管の血液量を増やし、水分を吸い上げます。
そのため、皮膚近くに留まる血液が増え、体内を巡る血液の量は少なくなります。
また、水分を汗にとられた血液は粘度が高くなり、スムーズな体内循環が難しくなります。
そのため、脳に届く血液が少なくなってしまい、意識が遠くなったり失神につながってしまうのです。
皮膚が温度が高くないと感じればこの現象は防げます。
エアコンで適度な温度に保つことは熱中症を防ぐのに効果的なのです。
水分の補給、適度な温度設定で熱中症を予防しましょう。
2016/06/16
チャドクガに刺されたらどうする?
木々の緑が美しい季節になってきました。
この時期にツバキやサザンカの葉の裏にいる毛虫、それがチャドクガです。
フサフサとした毛があり、触るとマズイ!と思わせる見た目をしています。
さて、このチャドクガ、迷惑な事に毒針の毛をまき散らします。
この毛は繊維のすきまからも入り込んでしまう極小サイズで、目には見えません。
さらに厄介な事に、釣り針のように先端が抜けにくい形をしています。
この毒針毛が皮膚に刺さり3時間程すると、赤くポツポツと膨れ上がり猛烈にカユくなります。カユさで寝れなくなることもあるようです。
処置はまず皮膚に刺さった毒針を取り除きます。
ガムテープで刺さった針を出来るだけ皮膚から抜き取り、水で流します。
手で払うと、手や他の皮膚に刺さって被害を拡げてしまいます。
その次にステロイドの塗り薬を使います。
チャドクガの毒はかなり強く、炎症を抑える効果が弱い薬では症状を抑え切れません。
また、カユミを止める飲み薬を使うこともあります。皮膚科を受診しましょう。
刺された直後は缶コーヒーやカイロを当てるのも応急処置としては有効です。チャドクガの毒は熱に弱く、約50℃で毒性を失います。
次回は衣類の処置と予防方法についてお話します。
2016/05/19